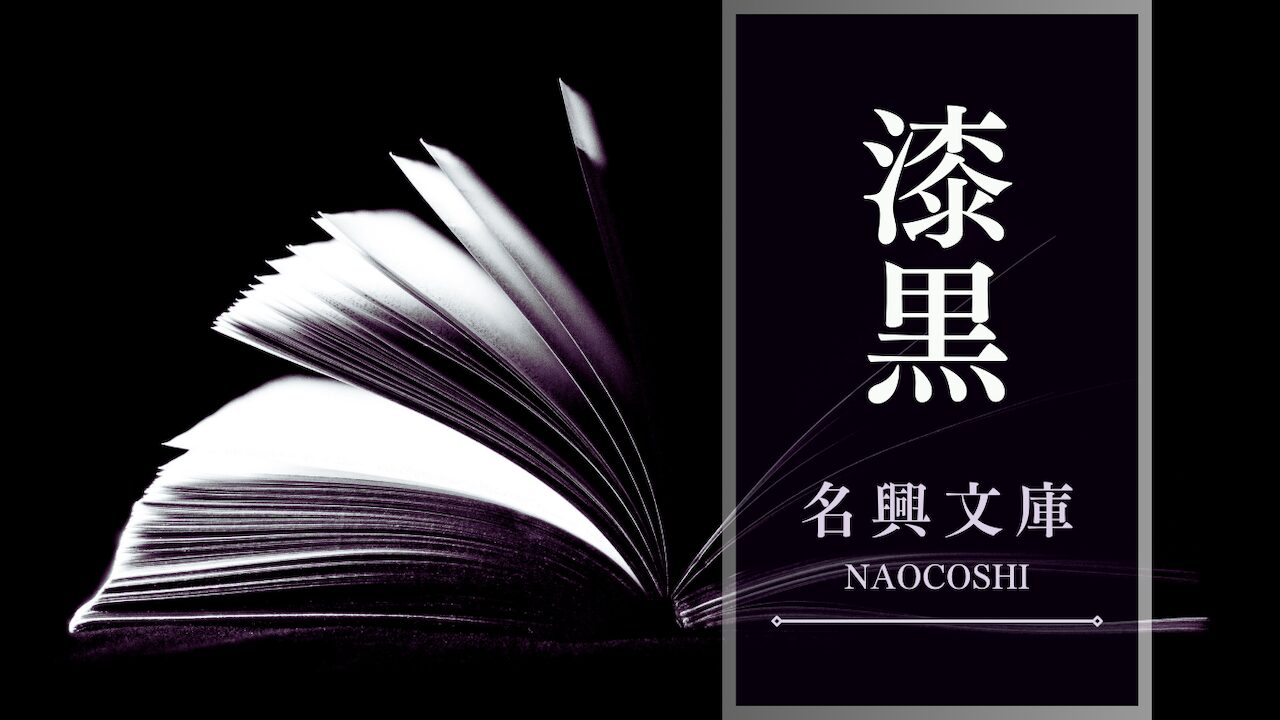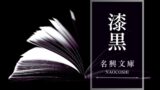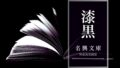感謝の御挨拶
『【第01回】名興文庫-漆黒の幻想小説コンテスト』令和7年8月末日をもって締め切りました。当コンテストの参加者の作者様方、お疲れ様でした!
最終的な参加作品数は135作品、文字数にして13万字を超える規模となり、初回のコンテストとしては上々の結果であるとともに、書籍化にも適した素晴らしい結果となりました!
昨今の小説界は二極化の傾向が強まり、一般の読者が気軽に手を伸ばしにくい状況があります。そんな時世の折、当コンテストはともすれば少数派でハードルの高い幻想小説を読みやすく多彩な作風に触れやすい1000字以内に収め、純文学的な幻想小説からライトノベル的な作風までを包含する、多彩な作品の可能性を提案する趣旨がありました。
結果として、幅広く素晴らしい作品が集まり、名興文庫としても独自性の高い提案としての書籍を刊行できそうです。
より詳しい選評・収録に関しましては年内をめどにアナウンスと発表をしていきますので、もうしばしお待ちください。併せて次の新しいコンテストの発表もご案内申し上げる予定です。お楽しみに!
それでは、参加された作者の皆様、お疲れ様でした! 次回もまた皆様の作品に触れられることを楽しみにしております。
七月度一次選評
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『緯度零度を超えて』|尾内甲太郎
ほど良く古式の文字表現に触れられつつも、壮大な漂流・継承・時の移ろいが描かれた物語。あるいは変質した神話のようにも読めるこの物語は、幻想譚として独特な光を放っています。
『裏戸を抜ける』|尾内甲太郎
有名漫画を想起させるモチーフのようでいて、全くそうではない物語。例えば神代の盗人は、予想外のやり方で結果を出すことがあります。それは盗みという行いに、良くも悪くも普遍性があるからであり、この物語もそれを思い起こさせます。
八月度一次選評
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『終わりの海を覚えてる』|葛城騰成
現世の終焉、果てとしてのユニークな海と、その海を俯瞰する者の物語です。この海の描写は独特で、リアルな悍ましさと暗さに満ちていますが、俯瞰者の、及び物語の最後のシーンに、それでも輝ける思い出と色彩が鮮やかに現れ、それは読む人に希望の光を感じさせます。
『タワー・オブ・フォース 花舞う剣士の旅路』|ラウンド
不思議な装いの剣士が見上げるのは、意味深な名前伝わる四つの塔の一つ。植物との関わりを感じさせる物語ですが、人に暦の必要性を気づかせたのは多くの場合、植物です。物語の始まりが多くの想像を掻き立てます。
『願いをかなえる石像』|江渡みきあ
タイトルにもある、願いをかなえる石像がもたらす意外な代価と、人々の変わらぬ願いが織りなす因果の物語。純粋に思えるそれも、実はとても卑小なものかもしれません。それでも自嘲気味の笑みには、皮肉だけではない優しさがあります。それは人を超えつつある視点かもしれません。
『神の庭を歩く者』|ラウンド
かつての神々の庭は放置され、零落した何かが彷徨うのみ。永遠に続く事の無い再生はいつかゆがみを抱えてしまうのでしょう。では、その帳尻を合わせる者は何者でしょうか?
『果てなき卓は虚無に満ちて。』|てぃえむ
幻想詩の趣もある、黄金の時代の終わりの物語。多くの神話の名詩が出つつも、それは比喩であり、それだけにこの物語は象徴的です。私たちはおそらく自ら選んで、虚無が差し込み始めた世界を歩いていますが、それは人の物語の始まりでもあります。
『神々』|夢幻
再来した神々の姿は古代の伝承の威容を全く失っておらず、破滅的でありながらも、どこかに教導的な希望を感じてしまうのは、我々が神々を必要とし続けているからでしょうか? 誰しも無縁ではない頽廃の空気が、この物語の神々の威容を引き立てている気がします。
七月度一次選評:Creative Writing Space掲載作品
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『王の子らの醒夢』|かぶき六號
西洋的な物語に見えて、実は仏教的な二種類の救済者の形を持った双子の王の物語です。寓話的な、あるいは皮肉な結末に陥らず、理想的な二人の王の出現によってもたらされた平穏は、東洋的な調和とも読み取れます。
『常夜の国』|ひら やすみ
おそらくは死者たちの物語。死者を仏、あるいは神として崇める事もある我々の文化圏では、死後の死者の役割も様々に考えられる。その営みの中にわずかに蘇る思い出はおそらく、かつて生者だった者の願いなのでしょう。
八月度一次選評:Creative Writing Space掲載作品
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『終わりなき残首』|吾輩はもぐらである
作中で災いをもたらす彼は、やがて自らの死を望み、かつての蛇に戻ろうと願います。しかし、蛇に首は無く、また蛇とは原始の知恵そのものであり、そこに善悪は本来ありません。彼の終わりなき生もまた、いつしか概念として不滅と化している可能性がありますね。
『篝火は森に道を遺す』|吾輩はもぐらである
連作的に他の物語とも繋がりのある構成です。破滅的な討伐・浄化はあまりに無常な結果をもたらしますが、それでもまだ道は篝火が照らしており、残された希望そのものです。途中まで積み重ねられた情報がすべて消し去られる流れは、この物語の無常をいっそう強めています。
『いつか巡りあう』|称好軒梅庵
『幻想博物誌』などに登場する無頭人をモチーフに、対になる『体の無い人』それぞれの旅立ちを詩のような構成で描いた物語。この世に生まれたあらゆるものは、つまるところその世の中や、あるいは誰かと繋がっており、多くのめぐり逢いがあるものだ。
『黒き子』|理乃碧王
力には代価が伴う。とてもシンプルな教導の物語の形ですが、この物語もまたそれをなぞっています。美しくも黒い女剣士はいずこへ立ち去ったのでしょうか? 背景がとても気になる物語です。
『虚夢の唄』|ゐで保名
古文のような口伝的文体で書かれた、雨または涙の始まり。世界とはしばしば意思のある仕組みとして描かれますが、その世界が生み出した小さき者たちから何かを学ぶこともまたあるのでしょう。これはそのような解釈での雨と涙の始まりです。
『翔 -天空の神-』|terra.
精霊の一柱が神格となる事もしばしば起こります。この物語はまさにそのような物語でしょう。何らかの理由で力を失ったものは、実は大いなる試練を超えて天へと飛躍することがあります。ロケーションの美しい物語です。
『廻 -Circle-』|terra.
めぐる命の営みが、この作者さんの特徴でしょうか? 色彩豊かなロケーションで流れていき、とても豊かな安堵感と共に読み終えられる物語です。タイトルはまさにその通りと言える詩的な幻想小説です。
『月 -見守るもの-』|terra.
主人公が話していたものは、月でもあり、そして……。冒頭のコミカルな演出が伏線としても機能しています。コミカルであたたかな禅問答のような物語ですが、まめに描写された状況はとても幻想的です。
『笔 -文字の奏-』|terra.
それは幻想的な揮毫か、あるいは始原言語を見出しているのか? あえて『笔』という字を用いる事で読者の想像に委ねる余地のある工夫が幻想性を双方向のものにしています。技法としては難しいようでいながら、読み取れる人には秀逸な仕掛けとして作用するでしょう。
『甦 -Fusion-』|terra.
ある幻獣の生誕、あるいは再誕の物語。この作者さんの一連の作品は全て、途中で壮大で美しい情景描写と、豊かな色彩が現れます。そして、主人公が何者であるかという謎を残しつつも状況が変化して物語が止まり、それは一瞬異なる世界を覗いているかのようです。
『冬のむすめ』|中野眸
民話に転じた神話のような、とても柔らかな幻想譚です。この物語において人間に対して優しいのは冬の太陽ですが、人と決して関わらない冬のむすめには、それを超えた深く冷たい慈愛があり、神格としての説得力があります。
『絵に描いた竜。』|嘉良崇
人の心に訴えかける物には必ず何かが込められているものですが、それが何かを感じ取って語るのは意外に難しいものです。絵画に通じていながらも、その壮大な過去を読み取れなかったのは、慣れでしょうか? それとも慢心でしょうか? 示唆に富むおとぎ話です。
『花竜流し。』|嘉良崇
解釈で言えば妖精郷のドラゴンでしょうか? 伝承や祭事の変化の中にある真実と、それに触れた少年の物語ですが、幻想性と共に教導を含むのは作者さんのスタイルでしょうか? それが少年・少女にもお勧めできる柔らかで美しい物語となっています。