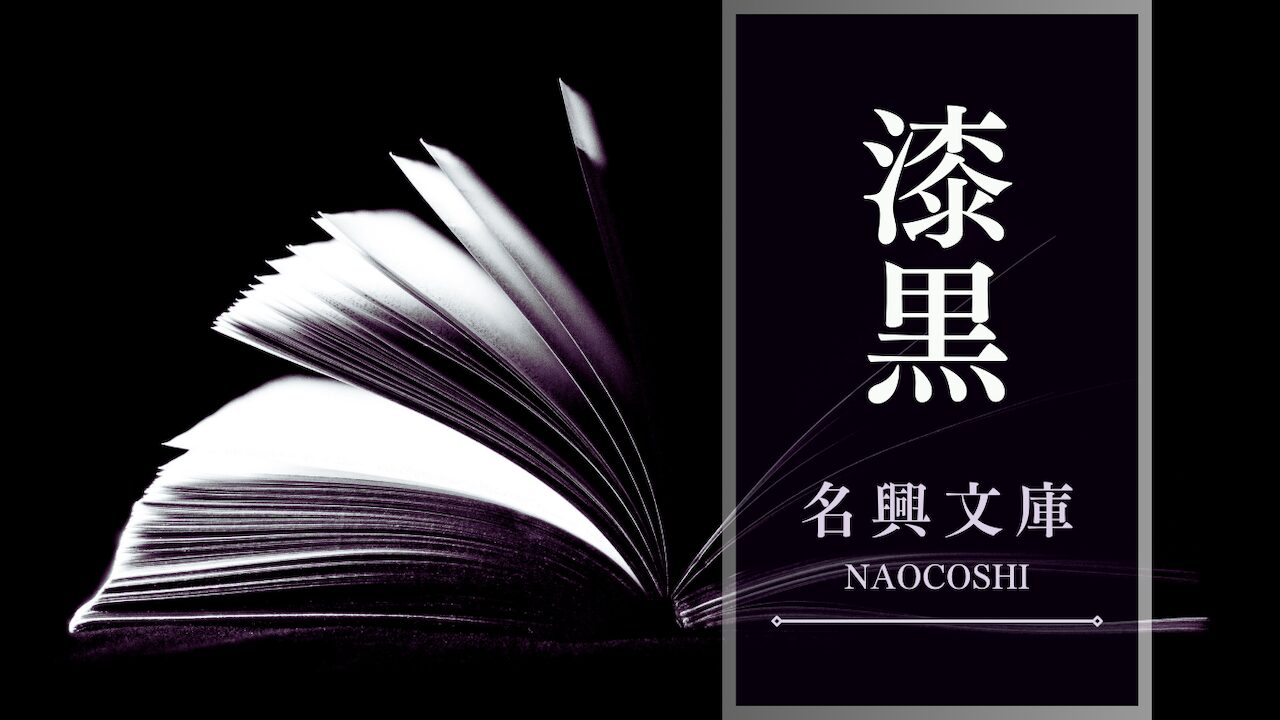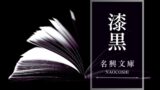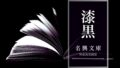所感
六月度の参加者の作者様方、お疲れ様でした! まず、今月も一次選評の公表が遅れてしまい、申し訳ありません。しかしながら今回も応募作品は多く、誠に嬉しい状態が続いております。ありがとうございます!
さて、五月度に勝るとも劣らない応募数ですが、美しい作品、深い作品が多く、解釈や精読に没入させられました。これは選考者にとって最も楽しい時間であり、『至福のひととき』をありがとうございますと申し上げたい心境です。
今回のコンテストのテーマになっております『幻想性』ですが、これは作者の文化資本の積み上げが無いと表現できないだけでなく、文化資本の積み上げが作品を通して非常に可視化しやすいものでもあるのです。そして、昨今の小説・出版不況の原因の一端には、ここ30年ほどの間、『小説の文化資本』を提示できず、小説による人生の成功体験を明確に示せなかったことも大きいのではないかと一考しております。
人は誰しも、『今より良くなろう』という思いを大なり小なり抱えているものですが、この思いの成就にあまり小説が存在感を示せていなかったのでは? ということですね。
一方、今回の数々の幻想小説は、外の灼熱の盛夏を忘れさせるような世界に満ちておりました。おそらくこのような体験をいかに読者に与え、それが何らかの糧となりうるかどうかが、大事なのではないでしょうか。 皆さんの作品はそのような可能性に満ちていると改めて思った次第です。
それでは、また次月に!
一次選評
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『鏡のうしろ』|茂垣
鏡をモチーフとした短い幻想譚ですが、複数の解釈の余地を残したままに綺麗にまとまっており、しかもそれは読者に想像の余地を多分に残して終わります。簡潔かつ高密度な幻想と言えるでしょう。
『時計の止まる町』|茂垣
幾つかの大きな震災を経た私たちは、『その時間』で時を刻む事をやめてしまった時計と、そのような人を──しばしば目にしており、この物語は時代性もあってかとても理解しやすいものです。時は定命の者を縛る枷であり、作中の老人を責める事は誰にもできないでしょう。
『水鏡の娘』|茂垣
彼女は何者だったのか? 古式ゆかしい表現をするなら罔象女のようなものでしょうか? 人と異なる彼女たちはおそらく単独でも在る事が出来そうでいて、人との関わりの余地を残す様子は、自然の中に我々が感じ取る暖かさの逆説かもしれません。
『時の箱』|茂垣
実は時間は存在せず、我々人間の目の前にあるのは永遠の現在かもしれません。しかし、流転していく現世の中で時間の経過を計る必要は低くはないでしょう。しかし、時を留める時計、戻す時計もあるかもしれません。それは確かに『時の箱』と言うべきものとなります。
『藁人形』|茂垣
タイトルにもある藁人形ですが、この物語では呪術としてのそれが独特な解釈として存在しており、土着の信仰のリアリティと禁忌を感じる事が出来ます。小さな構造の維持は、時に邪悪な幻想によって信仰に姿を変えて存在することもあるでしょう。
『雪氷に咲く月』|白川礼加
神秘や深淵がもたらされる時、それは触れたものの心に少なくない影響を与え、その未来を変えていく事は多分にあると思います。この物語はおそらく、星の記憶によってそれがもたらされる柔らかな幻想譚です。
『藍炎の刻印』|白川礼加
偉大なる武器の再生の物語ですが、作中でも触れられている通り、『武』ではなく未来を託す器物として剣が扱われ、作中の描写もまた原初の開抜のその前を思わせる希望の再誕となっている、美しい物語です。
『霞織の滝』|白川礼加
美しい契約・犠牲譚の形をとる救済の物語。大切な人との記憶を代価として選択したのはこれからの未来。織物に重ね合わせて語られるそれは失われましたが、未来という空白は希望が現れた事を意味しています。作者の美しい表現がそれをより鮮やかにしています。
一次選評:Creative Writing Space掲載作品
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『世界樹』|汐田大輝
はたしてそれは夢か現か、あるいは幻想か? 人ならざる者たちの領域にある世界樹を視界に収めていますが、しかしそれは幽世あるいは幻視ともつかないものであり、近年とみに現世的なエルフを再解釈した幻想に満ちた物語です。
『高原にて』|グリフィス
神話にはしばしば『獣の時代』『竜の時代』とも呼べるものがありますが、これはその争奪の神話です。壮大な流転の断片が語られて行きますが、それだけに一部の語彙は幻想性とかなり相性が悪く、そこはもうすこし考慮すべきかもしれません。
『アルホロスの森。』|嘉良崇
種族の再解釈の形をとった種族誕生にまつわる物語ですが、幻想的に収斂進化の過程と語源を表現する手法を取っており、その仕掛けを終盤まで気付かせない構成と雰囲気が優れています。
『世界の終わり』|グリフィス
最後のラテン語の一文は『永遠の美よ、光の輝きよ──沈黙に包まれし、世界の終わりよ』とでも解釈すればよいでしょうか? 世界の運行者としての天使のありようは、決して無慈悲ではないのです。ただ、人が誤っただけ。厳格の美のある終末譚です。
『真昼の丘の恍惚』|汐田大輝
解釈が深く分かれる良き幻想譚です。果たして神を肉塊となして調理したのはいかなる存在なのか? いずれにしても大いなる堕落や零落の背景が散見される物語であり、解釈の余地の広さと深さによって深遠かつ不穏な幻想が展開しています。
『心の鏡』|笛地静恵
白雪姫の物語と思いきや、意外な人物の視点で話は進み、メタ幻想小説として本来の白雪姫を斜めに見るような独白が展開していきます。皮肉めいた口調と共になされる洞察や、登場する小道具は童話を揶揄的な『おとぎ話』として見ることによって読者の幻想性がむしろ意識される構成となっています。
『鏡人』|尾内甲太郎
謎に満ちた世界観と共に、鏡を介した自他の境界及び自我の起源の怪しさに言及する物語。鏡像と自分のどちらが本当の自分であるか? つまるところそれを証明するすべはありそうで以外になく、ざらりとした感触の残る物語です。